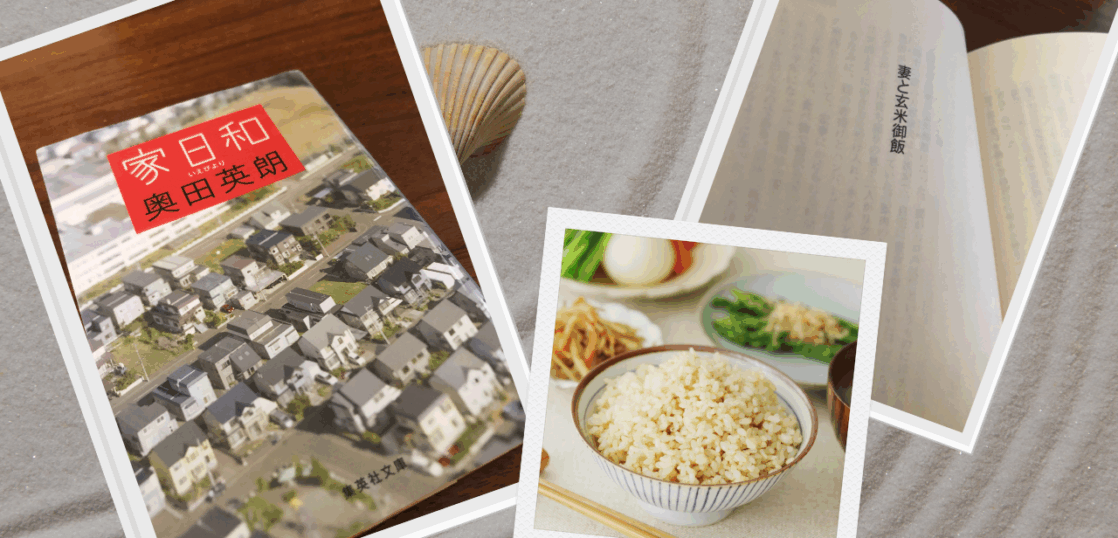こんにちは。環境のきく子です。8月に入り、猛烈な暑さ、本当にまいります。環境のきく子とて、エアコンつけずに暮らすのは無理そうで、もうエコエコ言っていられません。
さて、そんな夏。わたしはふと”環境にやさしい”をポリシーに生きているひとをどこか冷めた目で見たくなる疎ましさの正体ってなんだろう・・・とぼんやり考えていました。それで、なんかそんなことをうまーく表現していて面白かった短編小説を読んだことがあったことを思い出したのです。
”だったら、てめえのいえだけ汲み取り式便所に戻せって言うんですよ”
このセリフがやたらと印象に残っている小説。
たしか、ロハス(今はもはや聞かなくなったけど、2000年初頭にアメリカから始まった”Lifestyles of Health and Sustanability”というライフスタイルのこと)にはまった主婦たちが流木をつかって工作したりする話もあって・・・それのどこがエコなのか、みたいな感じで・・・
もういっぺんあの話が読みたい、そう思ったものの、何ていう小説だったっけ・・・タイトルが出てこない。作家の名前も・・・なんか広告関係の仕事か何かしてたけど独立して小説家になった人だったような・・・萩原浩だったような・・・(実在するのは”荻原”浩さんです)
で、荻原浩の作品をひたすら検索してもなかなかピンとこなくて、もうひとりいたじゃないの、すごい小説家、男性の・・・自問しながら、でも、やっぱり荻原浩さんだよ、きっと、、と思い込み、ずっと気になって数日間過ぎていく。その間、トイレに行く度に”エコに暮らしたいなら汲み取り式便所に戻せって言われちゃあ、おしまいよ”と居心地悪い気分になり・・・
しょうがないので、ふーむ・・・とスマホを開いて「流木 ロハス 汲み取り式便所 小説」と打ち込み、検索をかけたら、出てきたのです!ネタバレありの読書記録を書いてくれている個人ブログに、ぴたりと紹介していてそれは、
奥田英朗さんの『家日和』という小説の中の”妻と玄米御飯”という話だった!!
すぐさま、ネットで購入し、手元に届き、わくわくしながらページをめくりました。
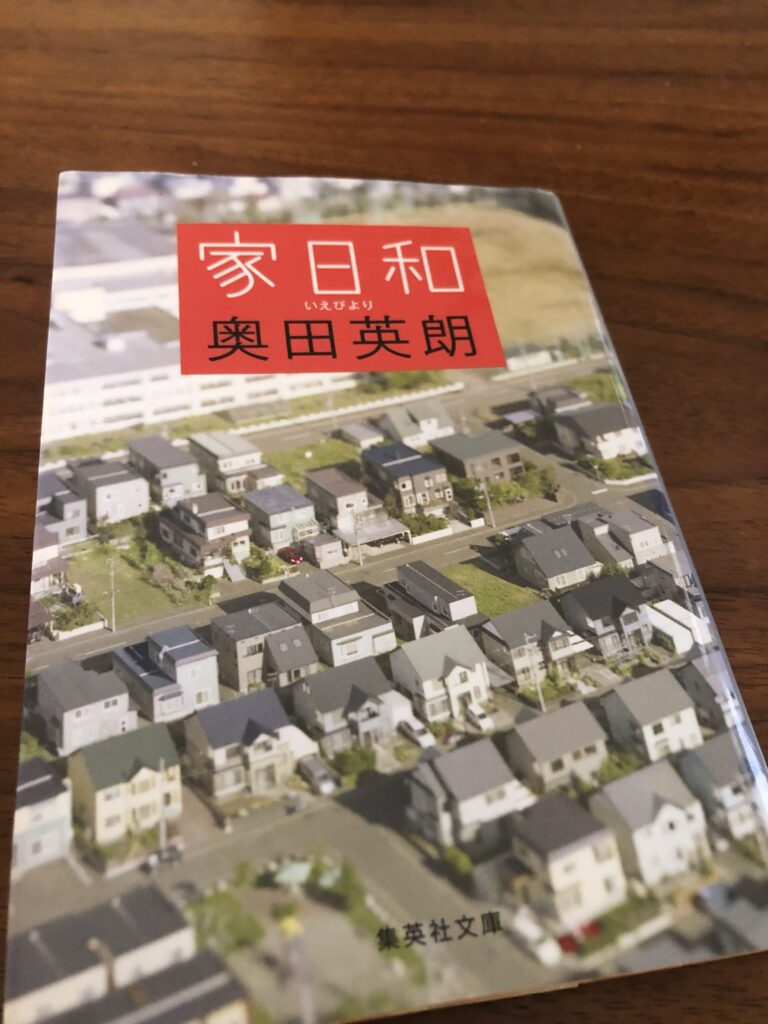
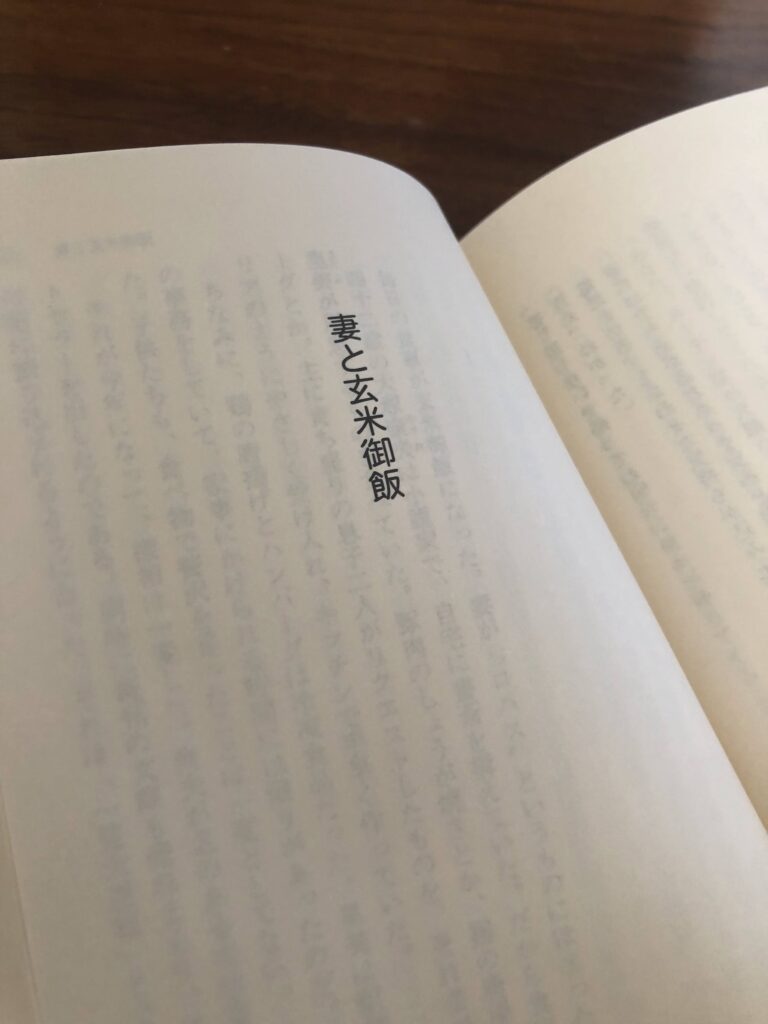
毎日の食事が玄米御飯になった。妻が”ロハス”というものにはまったせいだ。という冒頭から始まる。
主人公の大塚康夫は小説家で、賞をとったら忙しくなり印税で収入もアップ、その流れで、妻がパートの仕事を辞めてプチブルジョア的なライフスタイルに目覚め・・・環境意識が高くなり、白米から玄米御飯に代わり、肉はほんのちょっぴり・・・子ども達には不評・・・・そして、ナチュラルショップへ出入りするようになり、オーガニックコットンは最初に妻の琴線に触れた・・・というこれは奥田英朗さんの実話ではないかと思わせる。
ここには、主人公の康夫に代弁させている奥田英朗のそして普通に暮らしているその他多数の人たちの心のつぶやきがやたらに真っ当に書き出されているので、わたしのような”環境意識高い実践家”には、なるほどそう思われるのね、と無我夢中で読みとっていきました(笑)。
たとえば、最初の方に
”エコロジーの話は、嫌いでも正しいから困る”
とある。あーこれは私にもわかるかも。ストイックな意識高い系の人たちの話を見聞きしていると、こういう気分になるのは理解できるわ・・・
ロハス(LOHAS)って言葉は、ほんと死語になってしまいましたよね。もしかしたら今の若い人は知らないかもってくらい。冒頭の方にも書きましたが、これは20年前くらいにアメリカを筆頭に全盛期で、”Lifestyles of Health and Sustanability”の頭文字をとった造語で、日本でもけっこう流行ったのですよ。ロハスインターナショナル、っていう会社もあってそこはヨガスクールを開設し、そのヨガには20代の頃もわたしも何回か通った思い出があるな。健康で環境にやさしい持続可能なライフスタイルを取り入れることで世界を救える、というスタンスは今ではSDGsとかサステナブルっていう言葉に置き換えられたのかな・・・・
いわゆるブームというものになると、ブームは持続可能でなく、いずれ飽きられ廃れるのが”さだめ”なのかもね。
ロハスは、ブームだったから。
この小説にでてくる洒落オッティな広告会社経営者と元モデルの佐野夫妻の妻”優子夫人のような、裕福な知的美人が先導するから女たちは(主人公康夫の妻のように)ロハスブームについていったのだろう。”
彼女たちは、流木を使って電気スタンドや一輪挿しを作るために集まったりしていたのだけど、それを見て康夫は”時間を持て余した主婦のクラフト趣味かと思った”わけで、これがエコで地球温暖化防止に役立つなんてぬかしてると、スカしたオンナたちだと嘲笑されて当然だろう・・・うむうむ。
というわけで、この小説をさらに深堀りしていくべく、後編に続きます。