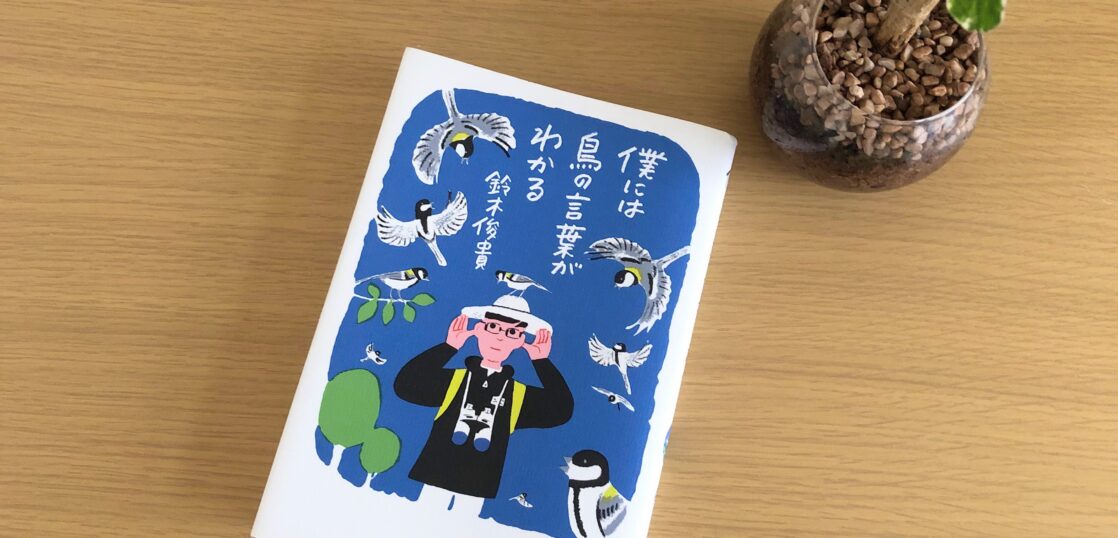”SNSで感動の輪が広がり、8万部突破!”という帯。シジュウカラの研究をしている東大准教授である鈴木俊貴さんが書かれたこの本は、今年の話題作ですね。
この本、私は6月に三鷹のよもぎBOOKSという小さな書店に別の目的(とある画家さんの個展を開催していたので)で立ち寄った時に、表紙の装画のあざやかなブルーとシジュウカラと著者と思われる人の素朴なイラストに惹かれて、衝動買いをしていた本でした。その日は、その本屋さんの魔法にかかり、たくさんの本を衝動買いしたので、積読状態となり、しばらく本棚に飾られていて気づけば秋。
9月下旬に、中学1年の娘の勉強を見ていて(塾に行かせていないので、あの手この手で家庭学習の声がけをする教育ママです・・・)、その日は国語の教科書ワークに取り掛かるという。娘が授業で読んでいるのが”言葉を持つ鳥シジュウカラ”という章でした。娘が「あのね、シジュウカラがジャージャーって鳴くと、それは”ヘビ”っていう意味をしているんだって」と教えてくれました。それを何気なく聞いていて、あっ!この話って・・・あの本と同じ著者ではないかい??と本棚から引っ張り出して見てみたら、やっぱりそうでした!せっかく娘も学校で習っていることだし、とわたしは『僕には鳥の言葉がわかる』の本を読むことにしました。
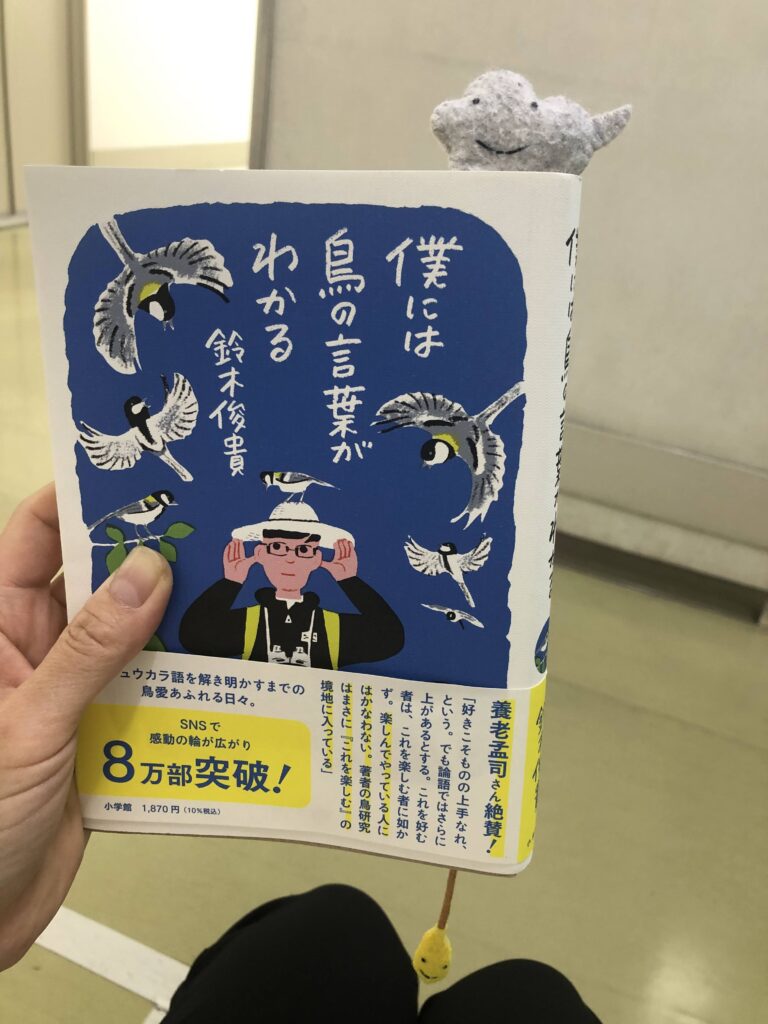
読み進めていくと、研究者の探求心ってすごい・・・と素朴に感心する・・・鈴木俊貴さんは、純粋にシジュウカラが好きすぎて1年間のうち10ヶ月は軽井沢の森に籠り、シジュウカラを観察し続けその年数は20年間。今では、東大の准教授となり、動物言語学という分野を開拓し、世界に向けて研究の輪を広げようと提案されているスゴイ方。
そして、この本のなかで著者の人柄とユーモアにあっぱれとなったのは、161~162ページ。
なんということだ…..。紀元前前から二千年以上ものあいだ、言葉を持つのは人間だけで、動物たちの鳴き声は感情表現だと決めつけられてきたのである。僕の尊敬してやまないローレンツ博士やダーウィン博士でさえ、そのように考えていた。身近な小鳥のシジュウカラにもこんなにいろいろ言葉があるのに誰一人としてその存在に気づいていない。
僕は思った。
このままでは人類は「井の中の蛙」である。他の動物たちの言葉に気づかずに、自分たちが言葉を持つ特別な存在だと思い込んでしまっている。
僕はカエルが好きなので、人類が「蛙」であることに特に問題は感じない。だが、「井の中」というのは大問題だ。カエルは虫を食べるので、井戸の中ではいずれ死に絶えてしまうだろう。井戸にいてよいのはオタマジャクシまでである。早急に助けなくてはならない!
↑
このカエルが好きだから、人類が「蛙」であることには問題を感じない。っていうところが思わず吹き出してしまう!!しかも、ご本人はきっと大真面目に「井の中」に大人のカエルになっても居残っているという人間の状態は大問題だから早急に助けなくてはならないと言っているのですよ。
いずれにしても、すごく衝撃的な問題提起だとわたしは、はっ!とさせられました。
うちの庭でもオナガが言葉を話していた!!鳥には言葉はあるのだ。
シジュウカラは色んな鳴き声をだし、ジャージャーという鳴き声は”ヘビ”を意味する、そこまで観察を続けて突き止めた著者の鈴木さんは本当にすごい。
そして、わたしもふとそういえば、ということを思い出しました。
今年の7月上旬にうちの庭に生えているハナミズキの木のまわりの電線に水色のしっぽが長い鳥、オナガが五羽ほど停まっていてギャーギャー何やら騒がしかったのです。何かとおもって見てみると、ハナミズキの木に巣を作っているではありませんか。

ありゃ・・・これはこれは・・・たしかにその数か月前からというか、うちの庭、向かいの家、隣の家、古くからあるうちから4軒は植木がけっこう植えてある一軒家なので年中、スズメやヒヨドリがピーチクパーチク鳴いているのだけど、この西側の玄関先でも鳥が鳴いていたといえばそんな気もしてきて、その鳴き声はオナガだったのです。
そして、この西側にあるハナミズキのすぐ後ろには、エアコンの室外機が置いてあるので、この7月上旬に5羽のオナガがぎゃーぎゃー騒いでいたのを見てわたしは「こんな暑いところで卵を温めてたら、ゆで卵になっちまうから別の場所に引っ越した方がいいぞ!」と言っているようにも聞こえたし、もしかしたら私が気づかない間にオナガは巣で卵を産み、孵化してその騒がしかった日は巣立ちの日だったのかもしれない・・・それか、わたしが巣を見たために「人間に見つかった!ここにはもういられない逃げるぞ!」と言っていたのかもしれないし・・・どんな会話をしていたかはわからないですが、オナガ同士で真剣に話していたのは確かです。
しかしながら、鈴木俊貴さんのこの本を読んで、今の今まで人間以外の動物には「言葉の概念がない」とされてきていたというのには驚きました。日本人のわたしが韓国語やペルシャ語、アフリカの言語など外国語が音にしか聞こえず、何を話しているか理解できないのと同じように、鳥や猫をはじめとした動物は会話をしているようにしか思えていなかったのに、学術的にそれは言葉ではなく「感情表現」に過ぎないものだ、とされていたのです。
『僕には鳥の言葉がわかる』(著:鈴木俊貴 小学館)P234はこのブログのテーマでもある環境とSDGsにも当てはまります。
いつしか人間は、自らの持つ「言葉」によって自然と人間を切り分けていった。「動物には言葉がない」「人間が最も高度な動物だ」「人間は自然を支配する特別な存在だ」と言葉を並べ、そう思い込んできたのである。
そして、とうとう動物たちの言葉を理解できなくなってしまった。それどころか自然とのかかわり方も、共生から利用へと変わってしまったのだ。今日解決されていない諸々の環境問題もこうした井の中の蛙と化した人間たちの暴走によるところが大きい、と僕は思う。このままでは、そう遠くない未来人類も地球も滅びるだろう。
この本は、とても軽快で純粋で楽しい本ですが、この234ページに一番大事なことが書かれているようにわたしは感じました。
この本に出合えて本当に良かった。鈴木俊貴さんという若い研究者が、20年の歳月をかけてシジュウカラを観察し続け言葉があることを突き止め、人間だけが最も特別な存在なわけではない、ということを世界にむけて発信してくださって、それに大きな賛同の輪が広がって・・・本当に素晴らしいことだと思いませんか。
タイムリーにも、この本を読み終わりそうな10月27日、たまたまテレビをつけたらあの徹子の部屋に、鈴木俊貴さんが出演されていました!!シジュウカラ愛を熱弁する鈴木さんに徹子さんも圧倒されていました(笑)
この本を読んでからというもの、鳥のさえずりや鳴き声を聴くと、あら?何の鳥かしら?と注目するようになってきたし、どこもかしこも最近は、コンクリート敷き詰めた住宅が多くなってきているけれど、植木などが庭にある、ということは生き物たちと共生している、ということにもつながっているんだなぁ、落ち葉掃きが大変、なんて思うこともあるけれど、なんのこっちゃ、生きているって素晴らしい、と思うようにもなってきたわたしは娘に「影響されすぎじゃん(笑)?」と言われています。
今日も、私の家の周りではヒヨドリが元気に泣き叫び飛び回っています。みなさんのお家のまわりにはどんな鳥がいますか?