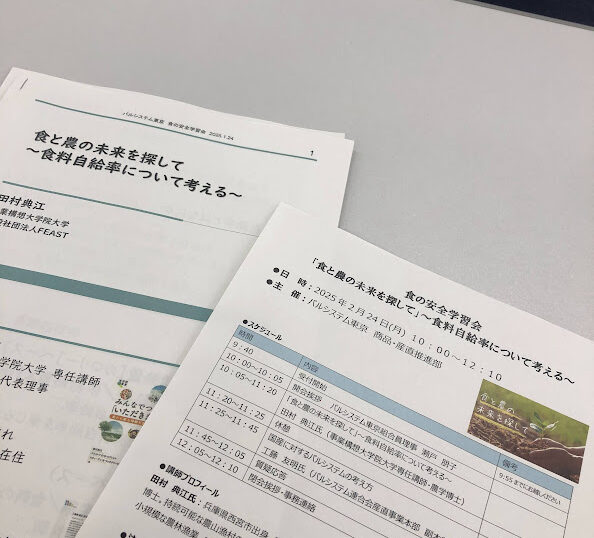こんにちは!KANKIKUこと環境のきく子です。KANKIKUをはじめたのは2021年。今年は5年目に入ります。4年間、日本の未来を見据えて、食料自給率の向上が急務だ!とわたしに出来ることを模索しながら発信や提案、実践をしてきましたし、専門書を読み漁ったり、大学の先生などが登壇されるシンポジウムや学習会にも積極的に参加して知識や知見を深めてきました。
先月は、我が家も利用している生協パルシステムが主催する食料自給率について考える学習会に足を運んできました。
昨年までは、とにかくお米離れを何とかしたい!と米粉の推進家としてクッキングワークショップを企画したり、Instagramでも米粉の魅力を発信してきましたが、昨年夏の終わりから、米不足によりお店からお米が消えた!というくらいお米が買えなくなって、その後収穫の時期を過ぎこの秋からは、お米の価格高騰。状況は変わってきました。
しかしながら、やはり高くても主食であるお米は必需品。お米を買い控えるという人もいるかもしれませんが、わたしのまわりでは食べ盛りのお子さんがいる家庭は月30㎏消費なんて方も結構いらっしゃいます。そして、わたしは思っていました。この騒動のおかげで、お米の大切さ、重要さに日本人は少なくともどんなに疎い人でも気づいたはず。米農家の高齢化による後継者不足、離農、さらには農家の時給は10円並み!?、そんなことでは担い手もできずどんどん衰退している、だから、値上がりしたとしてもお米の消費を上げて行こうという意識は肯定されるものだと。
大好きなお米、お米食べるとやっぱり落ち着くし、少なくともわたしの体質にはとても合っていて、食べないと体調が狂う。だからわたしもお米を毎日食べ続けるんですが、お米だけでなく全体の国内生産者の状況を考えると、素人のわたしから見ても食料自給率はこの、今の社会状況だとどうにも上がるとは思えない。
だって、なんだか色んなことが矛盾しているんだもの。
外国産の食料の安さと輸入量の増加、日本国民も不景気により安いものを買って家計を回していく、そういうシステムが出来上がっていて、高くても日本のものを買いましょう、というのも無理があるのは確か。お金に余裕のある人だけで国産の高いものを買って日本の一次産業を支えます、と満足する風景もなんだか斎藤幸平さんが言う「SDGsはアヘンだ、免罪符だ」という感じ。そして、日本では売れないので、日本で作った食品を輸入向けに出す、という貿易システム。なんか矛盾していると思うのは私だけでしょうか。
2年ほど前に、わたしは東大大学院で農学分野の研究をしていたというネットビジネスの起業家に起業相談をしに伺ったことがありました。日本の食料自給率に貢献できる事業をしたいのだけど、なかなかこれだ!というものがひらめかず壁にぶち当たる。何ができるのか自信がなくなっている、という趣旨の相談をした記憶がありますが、その時にその方は「食料自給率は見なくていい、当てになりませんから」とおっしゃった。「あの自給率の数字は、カロリーベースですよね、農林水産省が言っているだけにすぎないので、違う路線でやられた方が良いと思う」というようなアドバイスをいただき、なんでそんなこと言うのかしら??カロリーベースという非常にあいまいな38%という数字ではあるのは確かに理解できるけれど、38%で低いというのは事実なわけだから、あの数字は当てにならないなんて何よ、と腑に落ちないままではいたのです。
今回、久しぶりに、事業構想大学院大学で農学博士の田村典江先生というまた頭の良い方からお話を聞けるというので、食料自給率の問題がここ最近ではどうとらえられ、私はどうしたら良いのか理解を深めたい、と楽しみにしていました。
すると、自給率というのはそもそも何か、というお話から、食料安保という観点から歴史をさかのぼり、グローバル社会になったことにより食の問題が複雑化してきた、ということをしっかり教えてくださり、なるほど・・・ととても勉強になりました。
しかし、田村先生もわたしが以前にお会いした東大大学院卒の起業家と同様にさらに、わたしが疑問に感じていたのと同じように、この数字を上げるために国がどういう政策で進もうとしているのか道筋とか方向性が非常にあいまいだ、と話をされたのです。
色々、スライドを説明してくださりながら、一緒に考えていく流れで、最終的には、農学博士の田村先生が出したまとめの一つは
「食料自給率の数字に関しては、あまりにも実態がなさ過ぎてあまり見てもしょうがないので、食料需給に責任を持つ官僚以外は気にしなくていい」
ということでした。
驚きとともに、すっと納得しました。
そして、自給率の前に農地の保全のほうに視点を向けるべきではないか、という話にも、大きくうなづけましたね。
食料の生産と消費の在り方、食べることは生きること、そういうことを改めて向き合うと、小規模なものを丁寧につなげていくような食のビジネスはこれから大事なことだし、そういうふうに日本の農地の保全に貢献できることを自分は丁寧にやっていきたい、それしかできないのだろうな。
だって、25年前から変わらない議論をずっとしているんだもの。頭の良い先生方も皆、こう言うならそのとおりなのでしょう。
わたしには、十代のこれからの未来を生きていく子どもがいるので、責任を感じながら、やれることは数字を上げることではないという現実を受け止め、やれることをブレずにやっていこうと気持ち新たに決意しました。